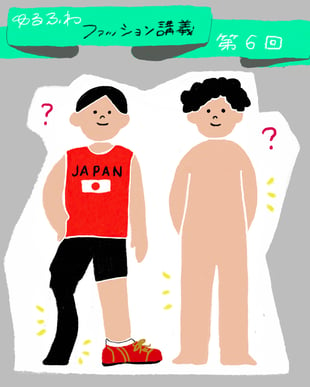Image by: FASHIONSNAP

Image by: FASHIONSNAP
「ゆるふわ大明神」の異名を持ち、長年京都を拠点に大学でファッション論を教える傍ら批評家・キュレーターとしても活動してきた京都精華大学デザイン学部教授の蘆田裕史氏が、「ファッション」や「ファッション論」について身近なものごとから考えるコラム連載。第4回は、今の若い世代にはその存在や功績があまり知られていない「日本の90年代ファッション」を再考。
ADVERTISING
目次
日本の現代ファッションを歴史化する
前回はファッション展の展示方法についてお話ししましたが、ファッション展⎯⎯正確に言えば美術館⎯⎯の役割は作品を見せるだけにとどまらず、「アーカイヴ」として機能する必要もあります。本当なら美術館がさまざまな作品を収集・保存することがベストなのでしょうが、日本の美術館ではさまざまな面(予算やファッションに対する価値観)で厳しいと言わざるをえません。せめて作品を価値づけ、カタログなどを通じて記録される展覧会がアーカイヴとして機能することが望まれます。
そんな話をしようと思ったのは、つい先日、ファッションデザイナーの永澤陽一の回顧展「Beyond Creation⎯⎯永澤陽一の創造と革新」(神戸ファッション美術館)を見たことがきっかけです。永澤は1990年代から2000年代にかけて活躍したファッションデザイナーで、当時はさまざまなメディアで取り上げられていましたが、いまの若い世代の方の多くは、たとえファッション好きであったとしても永澤陽一や「ヨウイチ ナガサワ(YOICHI NAGASAWA)」という名前を聞いてもピンとこないのではないでしょうか。これは永澤にかぎらず、2000年前後に活躍していた他のファッションデザイナーに関しても同じことが言えると思います。
そこで、今回のコラムでは、2000年前後の日本のファッションデザイン/ブランドの歴史化を試みようと思いました。ただし、あらかじめ断っておきたいのは、今回の話は綿密な調査にもとづくものではなく、僕の個人的な視点による歴史記述です。美術の場合でも、歴史を語るときにどの作家を取り上げるかには書き手の視点が多分に含まれ、「どれだけ売れたか」や「どれだけ人気があったか」はそれほど重視されません(とりわけ後者は実証するのが困難でしょう)。けれども、複数の書き手の視点による歴史記述が積み重ねられれば、最大公約数的にオーソドックスな歴史観が作られることになるはずです。ファッションに関しても同じことが言え、現代ファッションを歴史化するためにさしあたって必要なのは、さまざまな書き手がそれぞれの視点で歴史記述を行うことではないでしょうか。(文:蘆田裕史)
YOICHI NAGASAWA
「トキオ・クマガイ(TOKIO KUMAGAI)」でデザイナーを務めていた永澤陽一が1991年に独立し、立ち上げたブランド。翌1992年には毎日ファッション大賞新人賞を受賞。1993年に新ブランド「ノーコンセプトバットグッドセンス(NO CONCEPT BUT GOOD SENSE)」を発表し、同ブランドは『装苑』の常連ブランドとなる。2005年からは金沢美術工芸大学大学院で、2019年からは国際ファッション専門職大学で教鞭を執る。
80年代⎯⎯モノとイメージのあいだで揺れ動いた時代
さて、1990年代の日本のファッションデザイン史を記述すると言ったものの、1990年代以降の特徴を明らかにするためには、1980年代から話をする方がよいように思われます。歴史を理解するためには、文脈をおさえることが欠かせませんので。まず、最初に指摘すべきことは、1980年代までの日本のファッションデザインは、服そのもの、つまりモノ自体が評価の対象となっていたことです。
1980年代初頭にパリデビューをはたした「コム デ ギャルソン(COMME des GARÇONS)」や「ヨウジヤマモト(Yohji Yamamoto)」のいわゆる「ぼろルック」などは、衣服それ自体がインパクトを与えていました。両者の作品はしばしば「黒の衝撃」と呼ばれますが、実際にはフランスのファッションデザインの流れに位置づけられているのです。たとえば、コム デ ギャルソンとヨウジヤマモトがデビューしてほどなく、日本のファッションデザイナーを取り上げた記事がアメリカの『ヴォーグ(VOGUE)』に掲載されたのですが、そこではこのような記述が見られます。
東京でもっとも興味深い新進デザイナーのひとりに、コム デ ギャルソンの川久保玲がいる。彼女は日本のソニア・リキエルと呼ぶことができるだろう*¹。

「コム デ ギャルソン」の1983年のコレクション
Image by: Guy Marineau/WWD/Penske Media via Getty Images

「ヨウジヤマモト」の1984年スプリングコレクション
Image by: Guy Marineau/Penske Media via Getty Images
「黒の衝撃」は西洋ファッションとはまったく異なる価値観がパリに持ち込まれたかのように語られがちなのですが、この記事で川久保玲は「日本のソニア・リキエル」と呼ばれ、西洋ファッションの延長に位置づけられていたのです。この、「日本のソニア・リキエル」とはどういう意味なのでしょうか。それを理解するために、ソニア・リキエル(Sonia Rykiel)について書かれたものを参照してみましょう。
1974年、彼女[ソニア・リキエル]は初めて(…)縫い目を表にだしたアウトサイド・シームの服を提案した。第2の皮膚である服を裏返し、縫い目を見せ、服を「破壊」した。それから数年後、その表現形式を多くのデザイナー、とくに日本のデザイナーたちが心ゆくまで活用することになる*²。
ここでは、裏表をひっくり返し、縫い目を見せるというリキエルの手法が日本のデザイナーに取り入れられたと指摘されているのです。
コム デ ギャルソンとヨウジヤマモトがパリに進出しはじめたとき、たしかに一部の新聞や雑誌はコム デ ギャルソンやヨウジヤマモトのコレクションが提示するイメージに対して不快感を示すような論評を行ったのかもしれませんが、それが欧米の反応のすべてではないことが上の引用からも明らかです。
ただし、ひとつ注意しなければならないのは、衣服そのものについて語られるのと同時に、彼らの作品に日本的な「イメージ」が読み取られてもいたということです*³。先述の『ヴォーグ』の記事の別の箇所では、このように述べられていました。
彼女[川久保玲]は山本耀司やニコルの松田光弘と仲間であり、このデザイナーたちは新しいミニマルなコンセプチュアルアートとしての禅の簡素さ、あるいは「無」に忠実であった。
「禅」のようなわかりやすい日本的イメージを見てとるのは、オリエンタリズム的なまなざしを持っているがゆえのことでしょう。とはいえ、服そのものから読み取ることのできない(はずの)禅というイメージが見出されていたことも事実です。そう考えると、1980年代は「モノとイメージのあいだで」揺れ動いた時代と言うことができそうです。
90年代⎯⎯「おもしろさ」が価値となる時代
それでは、続く1990年代はどのような時代だったのでしょうか。おそらく1990年代の日本のファッションデザイン史を語る上では、裏原系がマストだと思われます。そして、僕がファッションに興味を持ち始めたのは高校生くらい(1994~1997年)なので、1990年代は自分の体験史としても語ることができる時代です。しかしながら、僕は体験史としては裏原系について語ることができないのです。というのも、当時僕は京都に住んでいたのですが、体感としては、関西では裏原系のブランドが東京ほど流行っていなかったように思うからです(個人の感想です)*⁴。
裏原系は「裏原(宿)」という東京の地名で表されていることからもわかるように、東京というローカルな⎯⎯けっして否定的な表現をしているつもりではありません⎯⎯場所に根ざした流行だったような印象を僕は持っています。もちろん、東京の流行は地方に影響を与えているので、日本全国でそれなりに流行っていたのだとは思いますが、関西はまた別の空気感がありました。それは、もっと奇抜なものを面白がるような空気です。今では考えにくいかもしれませんが、1990年代のファッションは、「かわいい」や「おしゃれ」だけではなく、「おもしろい」という価値が評価されていたのです。その代表的なブランドとしては「20471120(トゥー・オー・フォー・セブン・ワン・ワン・トゥー・オー)」や「ビューティビースト(beauty:beast)」を挙げることができるでしょう。
20471120とビューティビーストの特徴を一言でいうならば、アニメ的なもの、より直接的にいえばキャラクター性をファッションに持ち込んだことと言えます。ビューティビーストはコスパ(COSPA)とのコラボにより、アニメ⎯⎯セーラームーンからボトムズまで⎯⎯のキャラクターをプリントあるいは刺繍したアイテムを制作していましたし、20471120はエヴァンゲリオンやウルトラマンからインスピレーションを受けたコレクションを制作するだけでなく、「ヒョーマ(HYOMA)」というオリジナルのキャラクターをつくり、それがさまざまなアイテムに展開されました。


「コスパVSビューティービースト」と「銀河鉄道999」のコラボスタジャン
Image by: FASHIONSNAP
1990年代までは、ファッションとアニメはあまり親和性が高いジャンルではありませんでした。そのような状況のなか、20471120とビューティビーストによって、両者が結びつけられたことは先駆的な事例だといえます。2000年代後半から2010年代にかけて、アニメやアイドルといったサブカルチャーからインスピレーションを受けたり直接的にコラボレーションを行ったりするブランド⎯⎯「ミキオサカベ(MIKIOSAKABE)」、「クロマ(chloma)」、「バルムング(BALMUNG)」など⎯⎯がふたたび現れましたが、20471120やビューティビーストがその素地を作ったことは、強調してもしすぎることはありません*⁵。
20471120
1992年に中川正博とLICA(リカ)が「ベリッシマ(BELLISSIMA)」を設立後、1994年にブランド名を「20471120」と改称(その頃は商標登録時の読み方で「トライベンティ」と呼ばれていた)。「アート・モード・キャラクター」をコンセプトに、個性的なフォルムやデザインのウェア、アクセサリーを展開。サーカステントや遊園地を会場にユーモラスなコレクションを発表するなど話題を集め、原宿のストリートを中心に人気を集めた。
beauty:beast
独学で服作りを学んだ山下隆生が1990年に設立したブランド(当初のブランド名は「beauty&beast clothing」)。1995年に「beauty:beast」に名前を変え、東京コレクションに参加。2000年代以降はアシックスやオニツカタイガーなどのディレクターも務めた。
もうひとつのおもしろさ⎯⎯コンセプチュアル
1990年代のもうひとつのキーワードは「コンセプチュアル」です。これもまた違う「おもしろい」⎯⎯英語にするなら「funny」ではなく「interesting」が適当ですが⎯⎯という価値を持っていたといえます。たとえば「シンイチロウ アラカワ(SHINICHIRO ARAKAWA)」(荒川眞一郎)は1999年秋冬コレクションで、絵画のような服を発表しました。「絵画のような」といっても、実際にキャンバスに描かれたりしたのではなく、服が浮かび上がっているかのような生地が木枠にとめられたものです。そしてこれは実際に着ることのできるものでもありました。あるいは、「オー!ヤ?(OH!YA?)」(大矢寛朗)の本になる服/服になる本や、「ファイナルホーム(FINAL HOME)」(津村耕佑)が提案した「最後の/究極の家」となる無数のポケットのついた服などもありました。冒頭で触れた永澤陽一の作品にも、乗馬用のジョッパーズパンツを馬に穿かせたようなコンセプチュアルなものがあります。

「ファイナルホーム」による「最後の/究極の家」となる無数のポケットのついた服
Image by: FINAL HOME
ただし、このコンセプチュアルなファッションデザインは、マルタン・マルジェラ(Martin Margiela)やヴィクター&ロルフ(VIKTOR&ROLF)、フセイン・チャラヤン(Hussein Chalayan)などヨーロッパのファッションデザイナーの動向と重なるものであり、日本独自の潮流ではないことに注意する必要もあります。けれども、だからこそキャラクター性をはらんだファッションデザインとは異なり、欧米においても理解されやすく、受け入れられもしたのだと考えられます。実際、シンイチロウ アラカワとオー!ヤ?は、2001年にユトレヒトの中央美術館で開催された「Made in Japan」展に出展されていることからも、評価の対象となっていたことがわかります。
SHINICHIRO ARAKAWA
パリのステュディオ・ベルソーを卒業した荒川眞一郎が1993年にパリで設立したブランド。在学中はロンドンでクリストファー・ネメス(Christopher Nemeth)のアシスタントも務めていた。95年からは拠点を東京に移し、下北沢の商店街や東京大学の駒場寮など、それまでファッションショーの会場として選ばれなかったようなところでショーを行った。2000年、毎日ファッション大賞新人賞・資生堂奨励賞を受賞。
OH! YA?
三宅デザイン事務所から独立した大矢寛朗が1996年に設立したブランド。同年、東京コレクションおよびパリコレクションに参加。1999年からは『鉄腕アトム』をモチーフにしたブランド、「アストロボーイ・バイ・オーヤ(ASTROBOY BY OHYA)」を立ち上げる。
90年代欧米での評価の条件は「日本的フォルム」
1990年代の日本のファッションデザインの特徴を「キャラクター性」と「コンセプチュアル」に見てとりましたが、「Made in Japan」展に出展していた若手〜中堅のブランド⎯⎯「ジュンヤ ワタナベ(JUNYA WATANABE)」、「ゴム(gomme)」(真木洋茂)、「マサキマツシマ(MASAKI MATSUSHIMA)」(松島正樹)が出展していた⎯⎯を見ると、日本的なファッションデザインとして評価されていたもうひとつの要素がわかります。ただし、それは1990年代の特徴というよりも、コム デ ギャルソンやヨウジヤマモトの系譜としての評価です。
キュレーターのメリッサ・マッラ=アルバレス(Melissa Marra-Alvarez)はコム デ ギャルソンとヨウジヤマモトの服が「アシンメトリー」で「不定形」なものだと論じていますが*⁶、これは上述の「服そのもの」のフォルムの話です。だとすると、いわゆる御三家の次の世代のファッションデザイナーを評価する際にも、この二つのキーワードが重要になってくるはずです。20471120やビューティビーストが評価されずに、ジュンヤ ワタナベやゴム、マサキマツシマがなぜ評価されたのかを考えると、衣服そのもののフォルムが御三家の流れを汲んでいるかどうかが重要だったと言えるのではないでしょうか。
欧米で評価されるためには、「日本的なるもの」の特徴であるアシンメトリー性や不定形を見出すモノ自体を見るか、欧米の文脈と同様に服の背後にあるコンセプトを見るか、そのどちらかでないと1990年代は欧米に受け入れられなかったのだと思われます。
事実、20471120は1997年にパリでコレクションを発表しましたが、芳しい評価を得ることはできませんでした。彼らの作品の特徴であるキャラクター性は、欧米のファッションの文脈にとっては早すぎたのでしょう。しかしながら、その後2000年代前半になってようやく、2003年の村上隆と「ルイ・ヴィトン(LOUIS VUITTON)」とのコラボや2004年のタカノ綾と「イッセイミヤケ(ISSEY MIYAKE)」(滝沢直己)のコラボなどを嚆矢として、欧米のファッション業界でもキャラクター性が受け入れられることになります。もし20471120のパリ進出がもう少し遅かったら、また違う歴史が生まれていたのかもしれません。
ここでの歴史記述はあくまで僕の視点によるものなので、異論がある人も多いかと思いますし、「もっと重要なあのブランドが入っていない!」という意見もあるかもしれません。そういう方がいらっしゃったら、ブログなどでぜひ別の歴史観を提示してほしいです。複数の歴史記述が積み重ねられなければ、多くの人が納得する歴史を作ることはできないので。
本当は2000年代の話もする予定だったのですが、長くなってしまったので今回はここまでにします。もし評判がよさそうなら次回はこの続きを書きますし、そうでなければ別の話をするかもしれません!
gomme
「ワイズ(Y’s)」出身の真木洋茂が1989年に設立したブランド。身体をゴムで包むような服をコンセプトのひとつにかかげ、ギャザーやシャーリング使いをひとつの特徴とする。1993年から東京コレクションに参加し、1998年にはパリでコレクションを発表。
MASAKI MATSUSHIMA
「トキオ・クマガイ」でデザイナーを務めていた松島正樹が1992年に設立。同年、東京コレクションに参加し、1995年からはパリでコレクションを発表。ハイファッションの文脈で取り上げられることの多いブランドだが、初期の『FRUiTS』のスナップに頻繁に登場するブランドでもある。
*¹ Mary Russell, “JAPAN: A long way from the kimono”, VOGUE (Sep. 1982), Condé Nast, 1982.
*² パトリック・モーリエ『SONIA RYKIEL』(坂本美鶴訳)光琳社出版、1997年
*³ このあたりの状況については以下の論文が詳しいです。
安城寿子「コムデギャルソン、初期のコレクションをめぐる言説の周辺:同時代言説に見るその位置づけ・イメージと昨今の言説との距離」意匠学会『デザイン理論』47号、3-17ページ、 2005年
*⁴ 個人の感想ではあるのですが、同じような人は他にもいるようです。「雑誌で振り返る、おじさんたちの90年代ファッション座談会」では神戸出身の山田耕史さんが同じく裏原系を通っていなかったと語っています。
*⁵ このキャラクター性を抱えたブランドとしては、ほかにも「スーパーラヴァーズ(SUPER LOVERS)」/「ラヴァーズハウス(LOVERS HOUSE)」(ケン&メリー)などを挙げることができるでしょう。
*⁶ メリッサ・マッラ=アルバレス「西洋が東洋をまとったとき:川久保玲と山本耀司、そしてファッションにおけるジャパニーズ・アヴァンギャルドの台頭」『DRESSTUDY』57号、2010年
★今回のテーマをもっとよく知るための推薦図書
・伊藤忠ファッションシステム『ジャパニーズ・デザイナー』ダイヤモンド社、1999年
・『ファッション イン ジャパン 1945-2020』青幻舎、2021年
・深井晃子(監修)『+(プラス) Future Beauty』平凡社、2012年
・Tiffany Godoy, Style deficit disorder: Harajuku street fashion, Tokyo, Chronicle books, 2007.
・José Teunissen, Made in Japan, Centraal Museum, 2001.
(1990〜2000年代のブランドの資料となる本は少ない上に、ひとつひとつの記述が短いものがほとんどなんですよね… 最後の『Made in Japan』は国立新美術館のライブラリーに所蔵されているようなので、東京近郊の方はぜひ!)
edit: Erika Sasaki(FASHIONSNAP)
illustration: Riko Miyake(FASHIONSNAP)
1978年京都生まれ。京都大学薬学部卒業、同大学大学院人間・環境学研究科博士課程研究指導認定退学。京都服飾文化研究財団アソシエイト・キュレーターなどを経て、2013年より京都精華大学ファッションコース講師、現在は同大学デザイン学部教授。批評家/キュレーターとしても活動し、ファッションの批評誌「vanitas」編集委員のほか、本と服の店「コトバトフク」の運営メンバーも務める。主著は、「言葉と衣服」「クリティカル・ワード ファッションスタディーズ」。
◾️ゆるふわファッション講義
第1回:ファッション論ってなに?
第2回:可視化の時代におけるファッションとは?
第3回:美術展とは違う、ファッション展のみかた
第4回:「黒の衝撃」から辿る、日本の90年代ファッション再考
第5回:インターネット普及以後の日本ファッション⎯⎯平面性と物語性
第6回:私たちは“二つの身体”を持っている──ヌード、義足、厚底シューズ
最終更新日:
ADVERTISING
PAST ARTICLES
【ゆるふわファッション講義】の過去記事
RELATED ARTICLE
関連記事
RANKING TOP 10
アクセスランキング

Dior -Women's- 2026 Autumn Winter

DRIES VAN NOTEN -Women's- 2026 Autumn Winter