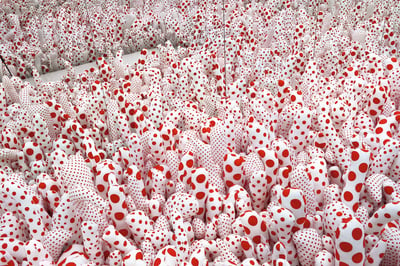批評家・ライターの谷頭和希による、「スタバらしさ」を通して消費文化を考える連載。今回は第1回目で語られた「矛盾」を「分裂」に置き換え、漠然とした「スタバらしさ」のイメージをより具体的に掘り下げていきます。(編集室H)※本連載は講義スタイルのトークイベントとして開催した内容を元に、後日編集したものを掲載していきます。
ADVERTISING
さて、スターバックスについての講義の2回目です。前回は、スタバが「どこにでもある」にもかかわらず「ここにしかない」という特別感を持つことを指摘しました。そして、その相反するふたつの要素を抱えるスタバを考えることは、我々をとりまく消費社会を捉える際の重要な視座になるだろうという話をしました(未読の方はぜひ第1回目をお読みください)。今回からは、この矛盾の具体的な姿を見つめながら、さらにスタバについて考えてみましょう。
「分裂」するスタバ
ここで、今回の話をわかりやすくするために、前回私が提起した「スタバに見られる矛盾」を「分裂」という言葉で言いかえてみたいと思います。「分裂」とはひとつのまとまりがいくつもに分かれることを呼びます。つまり、スタバはスタバとして一つの企業であるにもかかわらず、あたかもそれらが別の要素に分かれているような、そんな矛盾した状態を持っているのではないかということです。実は、スタバの「分裂」については、すでにある文献で指摘されています。それが、ブライアン・サイモンが書いた『お望みなのは、コーヒーですか?—スターバックスからアメリカを知る』(以下、『お望み』)という本。ここにスターバックスが持つ分裂が非常に明快に書かれているのです。それは、序章に書かれる次の言葉からも明らかです。
スターバックスはリベラルなラテ・ファンや保守的なカプチーノ愛好家、芸術からビジネス専攻の学生まで幅広い客層を獲得し、大衆的な客とニッチな客のどちらをも同じ空間に集めることに成功したのである。(『お望み』、p.17)
引用の後半で述べられている「大衆的な客」と「ニッチな客」を「同じ空間に集めることに成功した」というのは、まさに分裂した店内空間を表しているでしょう。前回も確認したようにスタバは今や日本で3番目に多い飲食系チェーンストアです。その点においては「大衆的」ですが、その店内にいる人々はMacのPCを開き、どこか「こだわり」が強い、ニッチな雰囲気を醸し出しています(これは私の主観も入っているかもしれませんが……)。まさにこれは、「大衆的であること」と「ニッチであること」の分裂でしょう。1つのスタバであるはずなのに、「大衆的であること」を押し出すスタバと、「ニッチであること」を押し出す2つのスタバに分裂しているのです。
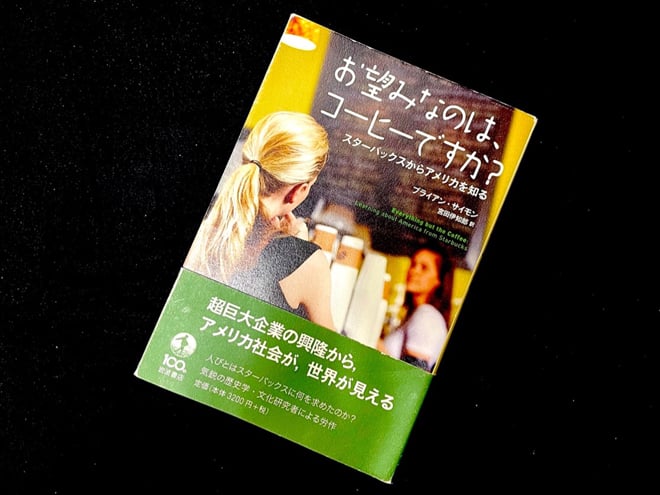
同書にはスタバが押し出す「サードプレイス」をテーマにした章もあります。「サードプレイス」とは、家庭でも職場でもない第3のコミュニティーとして、社会学者のレイ・オルデンバーグが提唱した概念です。スターバックスはこの概念を重要視し、店作りの重要コンセプトにしています。しかし、同書では、スタバがそうしたコミュニティーをほんとうに作っているのかが疑問視されています。
この本は序章を含めた全8章で成り立っていますが、各章がそれぞれ異なる「分裂」をテーマにしているとも読めます。では、この本で書かれているスタバの「分裂」はどのように捉えられているでしょうか。
「予測不可能性」としてのスタバ
『お望み』はスタバの「分裂」が書かれていますが、その「分裂」の捉え方はきわめて否定的です。それは、スタバについて書かれた他の本との比較をすると非常に際立ちます。ここからはスタバのある特徴をめぐって、『お望み』と他のスタバについて書かれた本を比較してみましょう。
そのときに注目したいのは、スタバの店内における「予測不可能性」という要素です。スターバックスで8年間マーケティングプログラムの作成と実行に関わったジョン・ムーアは以下のように述べます。
スターバックス体験は、あらゆる面において、日常の探検家を惹きつける魅力あるものとなるよう工夫されている。それも、友人や家族に語りたくなるほど魅力的に。(ジョン・ムーア『スターバックスはなぜ値下げもテレビCMもしないのに強いブランドでいられるのか?』、p.183)スタバの店内は、「日常の探検家」を惹きつけるようなものだといいます。探検では予測可能な出来事は起こりません。そんな場所に好んで足を踏み入れる探検家が満足できるような「予測不可能」な出来事が起こる空間設計をスタバは目指しているのです。
「予測不可能性」を重視し、客を探検家として扱うスタバのスタンスはこれ以外の本でも指摘されています。この「予測不可能性」が顕著にわかる一本のニュースを見てみましょう。
国内のコーヒー消費が頭打ちとなる中、大手のスターバックスコーヒージャパンが明日オープンする日本で初めての体験型の高級店舗を報道陣に公開しました。東京目黒区に明日オープンするのは、スターバックスで世界で5番目となる高級店舗です。[…]1階から3階がそれぞれ、コーヒー、紅茶、アルコール類を楽しむバーとなっていて、高さ17mの巨大な貯蔵庫や焙煎倉庫も併設しています。[…]体験型の店舗にすることで、コンビニエンスストアのコーヒーなどとの違いを打ち出し、新たな顧客を呼び込みたい考えです。 (ANN news CH『1200円のコーヒーも スタバが日本初の体験型高級店,2019年2月27日)
これは中目黒に誕生した「STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO」についてのニュースです。コーヒーショップなのに3階建てで、焙煎機や貯蔵庫もある、いわばコーヒーのテーマパークのような施設です。ここでも、スタバは新しい体験や驚きの体験を提供し、「予測不可能性」に満ち溢れた空間を形作っているわけです。ニュースの途中で出てきましたが、これはコンビニエンスストアのコーヒーとの差異化をはかるための出店でもありました。2013年にセブンイレブンが100円のコーヒーを売り出してから、コンビニコーヒーは爆発的に広まりました。安く、手軽にコーヒーを飲むだけであればコンビニで十分な時代が訪れたわけです。そのときにスタバが採った戦略が、「体験」という価値観を打ち出すことでした。そしてそれは、その店でしかできない「予測不可能性」に満ちた体験を提供するということでもあります。こうした試みもまた、先ほどの「探検」という言葉とつながっています。
「予測可能性」としてのスタバ
このように「予測不可能性」をスタバが意識し、多くの本で語られる一方で、『お望み』ではこうした「予測不可能性」に対して冷ややかな視線を投げかけています。同書ははっきりと、スタバには「予測可能性のブランド化」が見られる、と言っています。
「予測可能性」とは何か。これは、ジョージ・リッツァという学者が『マクドナルド化する社会』という著作で述べた言葉です。彼は同書で、マクドナルドで見られる効率的なシステム設計が社会全体に広がっていることを指摘し、資本主義による非人間的なシステムに人間が飲み込まれている状況を厳しく批判します。リッツァがマクドナルド化の要素として挙げた一つがこの「予測可能性」です。彼は、予測可能性について「マクドナルド化されたシステムは予測が可能」で、「作業も同じで、同じものを売っていて、そしてどこの場所に行ってもどの時間でも同じものが食べられる」状況だと語ります(ジョージ・リッツァ他『マクドナルド化と日本』、p.16)。たしかに、異なる地域にあるスタバでも、基本的にはメニューはほぼ同じですし、そこで提供されるコーヒーの味も均質化されているでしょう。その意味においては、スタバもまた予測可能性に満ち溢れているわけです。

お望み』では、このマクドナルド的な予測可能性がスタバを覆い尽くしていることが強調されています。
ポストニードの、ステイタス志向で、市民性が弱体化した世界の需要に応えてスターバックスが打ち出したのが、マクドナルド・スタイルの予期可能性をブランド化する新たな形だった。(p.63)
マクドナルドの予期(予測)可能性をひとつのブランドとして仕立て上げたのが、スタバの特徴だったとブライアン・サイモンは言います。
スタバの「分裂」をどう捉えるのか
しかし、さきほど確認したように、建前としてスタバは「予測不可能性」を押し出しています。それにもかかわらず、実際は予測可能性にも覆われている。この予測可能性と予測不可能性の分裂を『お望み』は指摘します。同書では次のように述べられます。
スターバックスはその合理性、つまり「マクドナルドな一面」をひたすらに隠そうとしたのである。(『お望み』、p.77)
この指摘からもわかる通り、同書ではこうしたスタバの分裂が、かなり否定的に捉えられています。スタバが我々に対して「予測不可能性」を押し出していても、その裏側にはマクドナルド的な「予測可能性」に満ちた企業の合理性によって支配される空間があるのではないか。スタバはそうした企業の合理性を隠してあたかもそれが無いように振る舞っている——。これが、『お望み』が一貫して主張することです。
しかし、私がここで考えたいのは、このスタバの「分裂」は否定的側面だけを持っているのか、ということです。スタバが「分裂」していることを肯定的にも捉えることができるのではないか。あるいは、肯定的でなくとも、それを分析的に捉えて、ただのスタバ否定論ではない形の論を展開することはできるのではないか。
「分裂」という魅力
そのときに私が参考にしたいのが、伏見瞬が語るポップミュージックの「分裂」です。どうしていきなりポップミュージックの話が出てくるのだ、と思われたかもしれませんが、伏見はポップミュージックについて次のように述べています。
ポップ・ミュージックは人を殺す力と人を活かす力を同時に持つ。経済や社会や国家に常に振り回される脆弱さと、他の何にも代え難い、誰にも奪えない強靭な生命力を併せ持つ。それが、ポップ・ミュージックという「分裂」した音楽産業である。その分裂は、個人と社会の間で戸惑い続ける、私たちの生の似姿だ。(伏見瞬『スピッツ論』、p.267-268)
ポップ・ミュージックは芸術であると同時に、それが社会全体に通用する大衆的なものであるという点できわめて「分裂」した存在だと伏見はまとめます。その上で、その「分裂」は、「個人」として生きつつ、同時に「社会」という厄介な存在に引き裂かれた私たち自身の姿でもあるというのです。だからこそ、人はポップミュージックを聞いてしまうし、そこになんともいえない魅力を感じてしまうのではないか。
ポップミュージックとスタバの分裂はもちろん同じではありませんが、ここに「分裂」という要素の魅力があります。したがって、『お望み』が語るように「分裂」しているからよくない、という語り方ではなく、むしろ「分裂」こそがスタバの魅力を作り出していると捉えることができはしないか。このような点から、伏見の「分裂」の捉え方を借りることでスタバが持つ「分裂」を肯定的に捉えることができるのではないかと私は考えています。
では、こうしたスタバの「分裂」はどのようにして生じたのか。それを捉えていくことで、こうした「分裂」をさらに深く考えていきたいと思います。そのために我々はまず、日本にスタバが上陸した1990年代に遡らねばなりません。
【文:谷頭和希/ライター・批評家】
最終更新日:
ADVERTISING
PAST ARTICLES
【ACROSS】の過去記事
RANKING TOP 10
アクセスランキング