

批評家・ライターの谷頭和希による、「スタバらしさ」を通して消費文化を考える連載の第3回目。前回はスタバが持つ「分裂」した特徴について、伏見瞬『スピッツ論』などを取り上げつつ掘り下げました。今回は日本一号店がオープンした1990年代について触れながら、分析を進めていきます。
※本連載は講義スタイルのトークイベントとして開催した内容を元に、後日編集したものを掲載していきます。(編集室H)
ADVERTISING
***
前回は、スタバが異なる方向に「分裂」していることを指摘しました。スタバは、予測可能性を高めて、マクドナルドのように世界中どこでも同じものが提供される空間を目指す一方、「驚き」に満ちた予測不可能な空間も提供しようとしている。そのように「分裂」しているのがスタバの空間でした。
スタバを考える際には、この分裂を捉えることが必要だと私は思います。今回からは、スタバの歴史を辿っていきながら、そこで見られる「分裂」がどのように始まり、そしてそれがいったいどのような特徴を持つのかを本格的に分析していきましょう。今回はまず、日本のスターバックスについて考えていきます。
はじまりに「分裂」があった
さて、そもそも日本のスタバはどのように始まったのでしょうか。日本のスタバ一号店は1996年、銀座に誕生しました。米・スターバックス社(以後、米・スタバ社)と日本の「株式会社サザビー(現:サザビーリーグ)」(以後、サザビー)が手を組んで生まれた一号店です。ちなみに、その4年前、1992年に成田空港で開店したスタバが、本当の日本1号店なのですが、それは経営的にあまりうまくいかず、すぐに撤退してしまいました。したがって、現在の日本のスタバの源流は、この1996年の店舗にあるといってよいでしょう。

スタバの日本一号店である「スターバックス銀座松屋通り店」は現在も営業を続けている。
最初に確認しておきたいのは、スタバが誕生した時代の共時性です。どういうことか、前回もご紹介した伏見瞬『スピッツ論』を参考に説明しましょう。ロックバンド・スピッツが「分裂」という言葉で語りうることを示した著作です。
この本で伏見は興味深いことを指摘しています。それは、スピッツがデビューした1990年代という時代の特徴です。スピッツのデビューは1991年。多くの人に知られるようになったのは1994年に「空も飛べるはず」を出し、1996年に「ロビンソン」を発表した辺りでしょう。この、スピッツがデビューした1990年代は日本において様々な「分裂」が顕在化しはじめた時代だと伏見は指摘します。具体的に、本書では、美術評論家として高名な椹木野衣の説が紹介されています。椹木は『日本・現代・美術』で、1990年代の日本美術の特徴を「分裂」だと述べました。椹木はこれを説明するために、村上隆が1990年代に制作した模型会社「田宮模型(現:タミヤ)」をモチーフとする作品群を挙げています。田宮は日本の会社ではありますが、アメリカの星条旗を思わせるようなトレードマークを持ち、アメリカ由来のプラモデルを扱っている会社なので、アメリカの影も非常に強い。そのようにアメリカと日本に引き裂かれた田宮をあえて意図的に作品の主題にしたのが村上隆だったわけです。伏見は、椹木の議論を紹介しつつ、スピッツもまた、「分裂」を表現したアーティストだったといいます(詳しくは、伏見瞬『スピッツ論』をお読みください)。
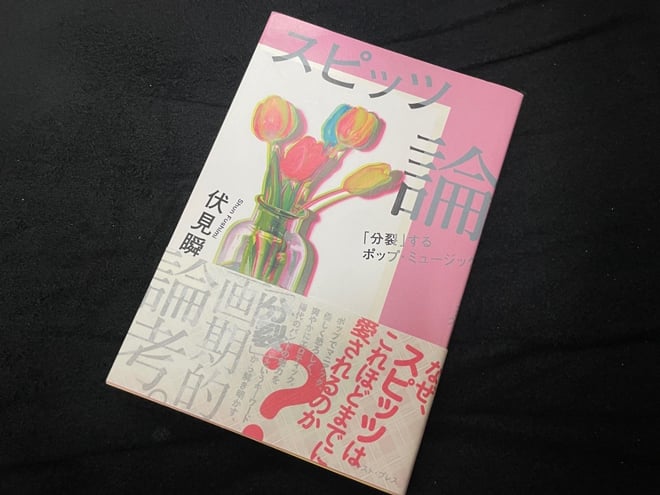
伏見瞬『スピッツ論』
1990年代、「分裂」の背景
「分裂」をテーマとしたアーティストが多く登場してきた1990年代、同じように「分裂」をその特徴として持ってきたスタバが日本に上陸したわけです。これは大変興味深い共時性ではありますが、その背景にはどのような事情があったのでしょうか。
これは私の仮説ですが、日本が「分裂」を意識せざるを得なくなった背景として、グローバリゼーションの進展や冷戦崩壊といったこの時期の国際情勢があるのではないでしょうか。1989年に冷戦が崩壊し、ソ連対アメリカというわかりやすい国際社会の構図が崩壊します。その結果として、戦後日本が大きく立脚してきたアメリカとはなんだったのか、ということが問われるわけです。そうした流れの中で、アメリカと日本の分裂への意識が非常に高まり、いろいろな表現の領域でこの分裂が意識されるようになったのでしょう。村上の作品も、「田宮模型」という日本とアメリカに引き裂かれた存在を主題にしていました。
ここで明らかになるのは、1990年代に言われた「分裂」が「日本とアメリカ」の分裂だということです。では、スタバにも「日本とアメリカ」の分裂は見られるのか。たしかにスタバはアメリカ・シアトルから生まれたお店です。その意味では、アメリカ由来のものを日本にも持ってくるという点においてそこに分裂が見られるといえるかもしれませんが、しかしこれだけではまだ不明瞭です。では、スタバの分裂は「日本とアメリカ」にどのように関わっているのか。この点を明らかにするために、より深くスタバが日本に生まれた経緯を見てみましょう。
サザビーとスタバ
スタバの日本上陸については、『日本スターバックス物語 はじめて明かされる個性派集団の挑戦』に詳しく書かれています。
銀座1号店が誕生する1年前、つまり1995年に、米・スタバ社とサザビーとの合弁により、スターバックスコーヒージャパンが誕生しました(現在ではスターバックスジャパンは米・スタバ社の完全子会社となっています)。サザビーは元々アニエス・ベーやカナダグースなどを展開する会社です。それがスターバックスとお金を出し合ってスターバックスコーヒージャパンができたわけです。サザビーの当時の社長は鈴木陸三。スターバックスコーヒージャパンの社長には、この陸三の兄の角田雄二が社長に就任しました。
先ほども触れた通り、現在はサザビーの手からスターバックスジャパンは離れていますが、サザビーのホームページを覗いてみると、どうもスターバックスっぽいなあ、と思います。ある種の雰囲気が非常に似通っている気がする。では、どんなところが似ているのか。ちょっとホームページを覗いてみましょう。サザビーリーグのホームページの1ページ目です。
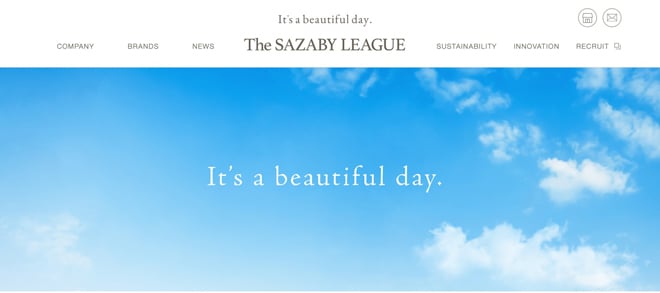
青空ですね。下にスクロールすると、こう書いてあります。
ライフスタイルのすべてに拡がる「LEAGUE」のビジネス。「LEAGUE」のビジネスは、「アパレル」「服飾雑貨」「生活雑貨」「飲食」「ビューティー」とライフスタイルのすべてにおよんでいます。[…]半歩先の視点や感性を忘れることなく、私たちにしか創れないモノを、私たちにしかできないやり方で、新しい価値観を作りながら「LEAGUE」として成長図を描いていきます。
これはスタバを考えるときも重要だろうと思いますが、これまでの連載でも触れたように、スタバはただのコーヒー屋ではない。つまり、「サードプレイス」というような概念、あるいはもっと具体的に言うと「サードプレイス」に表されるようなライフスタイルそのものを売っている。そのようなライフスタイルを売る志向は、明らかにこのサザビーがホームページで明らかにしている思想と相性がいいように感じます。これがスタバとサザビーの類似点のひとつ目です。だからこそ、サザビーはスタバを日本に持ってくることが可能だったとも考えられる。
ただ、こうしたホームページを見たときに感じるサザビーとスタバの類似性というのは、なんとなく私たちが感じる「かっこいい」感じ、批評言語としてはあまりにも感覚的で弱い言葉ではありますが、この「かっこよさ」にあるような気もします。スタバとサザビーの類似点のふたつ目、それが「かっこいい」ということ、です。
「かっこいい」ということ
この「かっこいい」という説明にならない言葉は、実のところスタバが日本に誕生する時の大きな要素になったようです。そもそも、鈴木はどうしてスタバを日本に持ってきたのか。言い換えると、スタバのなにに惹かれて、それを日本に持ってくることにしたのか。この点について『日本スターバックス物語』は次のように言います。
米国のスターバックスで調査報告を終えて帰国したサザビーのプロジェクトチームは、社長の鈴木陸三さんと専務の森正督さんにシアトルでのやりとりを報告しました。じっと聞いていた陸三さんは、強い光を放つ両目で僕を見つめながら立ち上がりました。そして、スターバックスのペーパーカップを手に持ち、僕の顔の前にぐっと突き出し、言いました。「これがかっこいいんだよ。このロゴとペーパーカップが」
ここで重要なのが先ほども取り上げた「かっこいい」という言葉です。なるほど、スタバを「かっこいい」とする感性は、鈴木も持っていたわけです。そしてこうした感性は私たちにとっても納得できるものかもしれません。

この本は次のようにも書いてあります。
(鈴木)陸三さんは、スターバックスを日本でやるべきだとも、やるべきでないともいっさい言いませんでした。その代わりに、スターバックスは「かっこいい」とだけ表現しました。
スターバックスを「かっこいい」と表現した鈴木は、最終的にスタバを日本に持ってくることにしました。そう考えると、やはり鈴木にとっては「かっこいい」という感性がスタバを日本に持ってくる重要な要素になったのでしょう。
「かっこいい」とはなにか
さて、私はさきほどごく自然に、スタバを「かっこいい」とする感性は今の私たちにも納得できるものだろう、と書きました。しかし、これは実に不思議なことです。というのも、「かっこいい」というのはこの上なく感覚的な言葉で、実態がある言葉ではないからです。
「かっこいい」という言葉について自身の経験を交えながら分析した劇作家の宮沢章夫は『80年代地下文化論講義』の中で、その言葉について「きわめて個人的な価値基準」と述べています。「かっこいい」という感性は、それぞれの人にとってまったく異なるように使われ、まったく異なる意味を持っている。
そうだとすれば、ここで鈴木がスタバを「かっこいい」と表現したときの「かっこいい」とはどのような意味で使われていたのでしょうか。宮沢は「かっこいい」という言葉はこれまで批評言語にはなり得なかったと述べ、あえてその言葉にこだわることでこれまでの文化論では語られてこなかった「かっこいい」の深層に迫りました。
ここでは私たちも、鈴木がスタバを「かっこいい」と表現したその意図に迫り、鈴木にとってスタバがどのように「かっこよかった」のかを考えていくことにしましょう。そして、今回の最初の話に戻るならば、実はこの鈴木が感じていた「かっこいい」という感性こそ、「日本とアメリカ」の分裂と大きく関係があるのではないかと思っています。
ヒントは、1950年代の湘南にあります。
【文:谷頭和希/ライター・批評家】
最終更新日:
ADVERTISING
PAST ARTICLES
【ACROSS】の過去記事
RANKING TOP 10
アクセスランキング

【日曜日22時占い】今週の運勢は?12星座別 <7月13日〜7月26日>

神保町のアメカジショップ「メイン」がオリジナルの商品開発で活路 女性客も増加

【2025年下半期占い】12星座別「日曜日22時占い」特別編












