Image by: FASHIONSNAP
「リトゥンアフターワーズ(writtenafterwards)」の山縣良和と美術評論家で多摩美術大学美術学部教授の椹木野衣の“談義”をお届け。ファッションデザイナーと美術批評家という一見相いれない関係でありながら、どちらも領域を縦横無尽に横断し、共に日本らしさに「うつろい」を見出している。ファッションが「流行」と訳されるなら、2人の「うつろい(流されるもの)」の視点は、日本のファッションシーンに新たな姿勢をもたらすかも知れない。連載最後となる三回目はファッション批評の勃興と衰退、あらわれては消える、幽かで、妖怪の様なファッションについて。
椹木野衣
美術批評家、多摩美術大学教授。1991年に最初の評論集「シミュレーショニズム」を刊行、批評活動を始める。 おもな著作に「日本・現代・美術」(新潮社、1998年)、「後美術論」(2015年、第25回吉田秀和賞)、「震美術論」(2017年、平成29年度芸術選奨文部科学大臣賞、いずれも美術出版社)ほか多数。1985年の日航機123便御巣鷹の尾根墜落事故を主題とする戯曲に「グランギニョル未来」(2014年)、福島の帰還困難区域で開催中の“見に行くことができない展覧会”「Don’t Follow the Wind」では実行委員を務め、アートユニット「グランギニョル未来」(赤城修司、飴屋法水、山川冬樹)を結成、展示にも参加している。「日本ゼロ年」(水戸芸術館)、「平成の美術:うたかたと瓦礫 1898-2019」(京都市京セラ美術館)など展覧会も手掛ける。
山縣良和
1980年、鳥取生まれ。2005年セントラル・セント・マーチンズ美術大学ファッションデザイン学科ウィメンズウェアコースを卒業。2007年にファッションレーベル「リトゥンアフターワーズ」を設立。「装うことの愛おしさを伝える」をコンセプトに、既成概念にとらわれない様々なファッション表現を試みる。2009年にオランダ・アーネム・モード・ビエンナーレにてオープニングファッションショーを開催。2015年には、日本人として初めて LVMH Prizeにノミネート。また、 デザイナーとしての活動のかたわら、ファッション表現の実験と学びの場として「ここのがっこう(coconogacco)」を主宰。多くのデザイナーやアーティストが輩出し、2021年には、第39回毎日ファッション大賞 鯨岡阿美子賞を受賞。近年の主な展覧会出展に、2017年「装飾は流転する」東京都庭園美術館、2019年-20年「アジアのイメージ」東京都庭園美術館、2021年「ファッションインジャパン」国立新美術館、2023年「ミレーと4人の現代作家たち」山梨県立美術館など。

ADVERTISING
ファッション批評は存在し得るのか
ー椹木さんは批評家ですが、ファッション業界でも2010年頃にファッション批評が盛り上がり、その後徐々にその勢いは窄んでいきました。
椹木:これはファッションに限った話しではないと思いますが、商業性が前に出れば出るほど、批評は危うい立場に立たされるのではないかと思います。たとえば、映画や音楽は美術と比べて産業規模がはるかに大きいですよね。美術は日本では産業というより教育に近しい関係を持っているので、そこで批評がかろうじて残りうる余地があるのだと思います。
山縣:映画や音楽のように、もしくはそれ以上に、ファッションも「産業」という性質を強く持っていると思います。先ほども話しましたが、ファッション表現の背後には、多種多様且つ多くの技術者との協業で成り立っている側面が強く、長い時間をかけて複雑な巨大産業へと発展しました。なので、事業や仕組み、構造に否定的と見なされる要素は、たとえ批評的であってもあんまり受け入れられづらい状況下にあり、業界内部からの発言が言い辛かったという印象です。

椹木:商業的な尺度が強くなればなるほど、本来が辛口である批評は、「営業妨害」や「名誉毀損」とみなされかねないリスクを抱えています。これは、美術館で燻蒸のように衛生を徹底するとなにもできなくなるようなことと繋がっている気がします。「コンプライアンス」を過度に徹底すると「表現」が何もできなくなってしまうのともよく似ている。でも、批評は本来、文芸の世界から生まれて、創作(作り手)があれば必ず批評(読み手)があるという一対のものだから、もの作りである限り商業性以外にどの分野でも必ず必要となるはずのものなのですが。

ー「創作と批評」はセットという言説は、文芸に限らずすべての創作(クリエイション)にも繋がる話のように感じます。
山縣:僕も基本的に同意します。どの世界にも批評家の不在による批評性のない業界は健全だとは思いません。残念ながらファッション批評の土壌が出来上がっていない世界では、批評されることに免疫がなく、単なる「営業妨害」とみなされてしまいがちなのかなと思います。
椹木:正当な批判というのは批評の本質で、本来は受け入れられるべきものだと思います。ところが、批評の役割が見えにくくなると、それが「非難」と受け止められてしまう。


ーでは、非難と批判の違いは?
椹木:ある文章を批判と受け入れるか非難として責められていると感じるかは受け取る側の主観にもよるので、はっきりとした線引きが難しいところもありますが、批評家の中では批判と非難とのあいだには明確な区別があります。ところが、ここに商業性(売り上げ)や広報性(動員)のような産業的尺度が大幅に入ってくると、批評も非難とあまり変わらないノイズのように受け止められるようになってしまいます。けれども、批評を欠いた創作は必ず行きづまるし、もしくは最終的には誰にも「文句」を言わせない商業性にまるごと飲み込まれてしまうでしょう。
ー山縣さんは批判されたとしたらどう受け止めますか?
山縣:発表している以上批判は覚悟しなければという気持ちは常にあります。しかし僕も強い人間ではないので、力を込めた作品であればあるほど、落ち込んだり、傷ついたりするとは思いますが。
椹木:世の中には風潮的に「受け取る側の心理」の方を重要視する流れがあります。すると、批評はますます難しくなってきます。100%世の中の誰も微々たりとも傷つかない、好きなものを「推して」いれば良いとなったとき、果たして表現が成り立つのかどうか。

椹木:これは先の商業性というのとはまた異なる角度の話になりますが、税金で運営されている美術館で開かれている展覧会では、学芸員や研究者の「主観」が一番ダメとされています。公金を使って主観で実証性の無いものを発表されては困るので、原則としては「成果報告」として展示がなされます。一方で、批評で一番大事なことは主観なんですね。ところが、心の中でどう感じたかは本来、他者とは共有できません。批評は、それを文章にすることでかろうじて共有を可能にしようとする「賭け」に近いものなんですね。
山縣:成果報告や実証性、客観性は関係ない、と。
椹木:少なくとも僕が批評として書いているものは、なにがしかの成果報告ではないし、実証性や客観性よりも文芸としての印象や主観の言語化の方が出発点となっています。実際、僕は批評家であっても学者でも研究者でもありませんから。

山縣:ファッション批評の状況的難しさの一つには、ファッション批評の射程の広さや曖昧さもあると思うんですよね。射程というのは、単に衣服への批評なのか、それとも髪型やアクセサリーなどの服装に対してなのか、またはファッションショーのようなコレクション自体やブランドの活動全体へのものなのか、はたまた現実での流行性へのものなのか。あまりにも複合的で複雑な性質をもつ、という意味です。ファッションは生き物のような側面があり、物質や物体の集合体に魂のようなものが吹き込まれることで、その集合体にファッション性が生まれるもの。コンセプトを持ちながらも、ガチガチのコンセプト一辺倒なファッション表現にはファッション性が宿りづらかったりと、なかなか単純ではありません。創作におけるプロセスも、意味性と無意味性を敢えて複合的に混ぜながら進めていく傾向があります。

椹木:おっしゃる通り、作品というのは簡単に言語でまとめられるものではありません。だから、あまり細部に拘泥しすぎると逆に批評にはなりません。僕の場合は、むしろ自分の中のより大きな文脈の中で作品がどういう意味を持つのか、というところから文章化に取り組みます。
ー「より大きな文脈」とは具体的に?
椹木:批評が成り立つための最大値として自分自身を形成する背景になっているものです。例えば「火山の噴火は人類に何をもたらしたのか」という問題です。そういう事象と照らし合わせた時に、ちょっと唐突かもしれませんが「この作家が行っている試みは、この地球上で何を意味しているのか」といふうに考えます。こうした思索をめぐらせていると「昆虫が巣を作ること」と「人が表現と称して何かを作る」というのはあまり境目がなくなってきます。それを自分が有限な主観で受け止め、なんとかして言語化する作業が僕にとっては批評なんです。僕が、山縣さんに「絶命展」でお会いして、その後も継続的に関心を持ち続けているのも、山縣さんの作品がどこかで僕の中のそう言った「大きな文脈」と響き合っているからです。
山縣さんは鳥取のご出身で、鳥取は水木しげるの生まれ故郷でもあり、「妖怪の町」として名高い境港があります。他にも、広大な砂丘や日本海などの「文脈」を持って作品を見ます。だから、素材やルック以前に、僕の中でそういうものを受け止めるための風土や文脈として、「批評」が機能します。

山縣は2021年に発表したコレクション「writtenafterwards 12th collection Gassho -Hidden Archives-」の一部を長崎県美術館で先行公開したことを皮切りに、展示会や長崎県五島列島の島を巡るプロジェクトなどを始動している。
山縣良和のクリエイションに見る儀式性、岡本太郎を例に
ー「火山の噴火は人類に何をもたらしたのか」という命題に関しても、山縣さんが近年クリエイションの対象にもしている長崎県は、雲仙岳という大きな山が“文脈”になってくれそうです。
椹木:僕が近年繰り返し訪ねている雲仙・普賢岳は、1991年の大火砕流災害で多くの人が亡くなった場所でもあります。2021年には「雲仙」をテーマに捉えた展覧会も開きました。そういう展覧会が成り立つ背景には、あの山に通っているうちに「火山の噴火と遭遇した人の中に、表現者として覚醒した人が多くいる」ということを知ったからです。「覚醒」というのは、必ずしも美術家ということではなく市役所の職員の方や、教員の方の中に火山の噴火に接することで表現を始めたというようなことで、実際そういう人がたくさんいらっしゃるんです。そして、そのどれもが僕にとっては批評的にたいへん刺激的なものだった。おそらく、火山の噴火にはそういう性質があるんだと思うんですよね。
山縣:僕の父方の実家は雲仙・普賢岳の近くで。噴火後間もない頃に長崎の実家に帰った際も、その風景を目撃して、衝撃を受けた記憶があります。

writtenafterwards 11th collection < For Witches >

ー「鳥取は妖怪の街である」という“文脈”が、ダイレクトに現れたものも、山縣さんのクリエイションの中にはあります。富士山もそうですが、山縣さんは、日本の普遍的な象徴としての「山」や「妖怪」「神」ではなく、うつろいやすさの象徴として日本的なものを取り込むのが上手いなという印象があります。
椹木:妖怪という概念そのものが、そもそもとても日本列島的ですよね。西洋のキリスト教圏には一神教の絶対神がいて、唯一の正義として語られている。それに当てはまらないものは“異端”になり、異端審問にかけられ、悪魔やその手先として排除される。そういった二重構造は日本列島にはない。各地各所に風土に応じた妖怪がいて、どの妖怪も日本列島の中心ではないし、逆に言えば、森羅万象なんでも妖怪になりうる。そういう、多神教……といっても「神」でもないんですけど、そういったものがウヨウヨしていて、時に応じて現れたり、消えたりする。そういう移ろいやすさが日本列島の特性だと思うので、そういう風土と、ファッションという「流行」は、日本列島のアートと繋がりやすいのではないかと思うのです。

2013年春夏コレクションwrittenfatrewards 7th collection < The seven gods>に登場する「熊手」をモチーフにした「七服神(しちふくじん)」。
ーファッションショーにおいても、幕から着飾った得体の知れないモデル(妖怪のようなもの)がランウェイを歩き、人々を驚かして帰っていくというのはある種、百鬼夜行的だなとも思います。
山縣:僕の根源的な感覚に「妖怪や神様など、人間ではないものも全て含めて、それぞれの存在が“ここにいてもいい”」と思えるようなことが表現したいと強く思っています。「着ることができない服を作るのは何故ですか?」とよく聞かれるのですが、決して闇雲に気を衒った表現を行なっているわけではないですし、“着る”という行為がいわゆる「人間の日常生活」のためだけと捉えていません。日本ではハレとケという捉え方がありますが、ハレ着の文化史を眺めると、非常にバラエティ豊かな神様や妖怪に扮する衣装が見られます。僕は一瞬でも着られたら衣服であるということを方々で言っていますが、実際に儀式や催事の一時のみで着用されるものも多く、催事が終われば破棄したりします。
椹木:山縣さんのファッションショーに登場するブリコラージュ的な衣装は、シャーマンなどの呪術的な振舞を彷彿とさせますよね。

山縣:歴史的に言えば所謂「祭」などの芸能に繋がっていくし、祭は、他界から来訪するものを招き入れる儀式でもあります。東アジアでは、折口信夫の云うところの「まれびと」信仰がありますが、まれびとは、新たな価値観を作り出して去っていく存在。ファッションをやっていく上では「新たな価値観を作り出して去っていく」ということはとても大事なことだし、そういうことを考えていると、ファッションも権力者からの垂直構造だけではないところからもたらされるものもあるのでは、と思っています。

椹木:儀式ということでいうと、岡本太郎が「美術」という言葉をひどく嫌っていたんです。「美術」というのは、保存が前提になっているけど自分が重要視しているのは体験であり、体験が喚起されればモノとして永続はしなくてもよいということを言っています。彼は儀式ではなく「呪術」と形容していましたが、芸術で最も大事なのは呪術性だということを強調していて、それにとても近いと思いました。儀式・呪術とは、つまるところ「祝祭」で、夜の夢のようにはかなく、幻の様に消えてなくなってしまうものです。
山縣:ファッションと呪術というのは、語感でいうと乖離がある様に感じるかも知れませんが、存外遠くもないですよね。

山縣良和と綴るファッション表現のかすかな糸口
ー今回の展覧会では「山縣良和と綴るファッション表現のかすかな糸口」ですが、「かすか」という言葉にも、妖怪や祝祭の様にフワッと消えていくというニュアンスがありますよね。
山縣:最初、「幽かな(かすかな)」の表記にするか迷ったんですよ(笑)。
椹木:今回の展覧会で言うと、第0章のバックヤードから始まり、地下に潜りながら暗く曲がりくねった狭い回路を歩き、最後、光に包まれた広い展示室で赤子という新たな命に辿りつくというのは、儀式ということで言えば「胎内巡り」を想い起こしました。洞窟を抜けると外光が差していて、そこからもう一度エレベーターを使い、地上に戻ることで「アーツ前橋」の外という、ありとあらゆることが起きている「現実」に戻っていく。展覧会という儀式を通じてもう一度生まれ変わるというか、そういう生と死の循環を感じました。

最後の章は山縣が目下必死になっている「当事者ごと」である育児の現場を着想源にした新作<It’s Alright To Be Here>が展示されている。
ー山縣さんの今までのクリエイションを思うと、新作として最後の部屋に自分の子どもを着想源にした直球の作品を展示することは、少し意外に感じました。
山縣:僕自身の心の変化なんですかね。普段はプライベートを表へ出すこと自体はあまり積極的ではないのですが、自分の中にある慣習を打ち破る必要性に駆られたクリエーターとしての意地のようなものだったのかもしれません(苦笑)。いつもは文化、歴史など外側をリサーチしながら進めていくのですが、今回は公私ともにあまりにも時間がなく、そのような状況で社会とリンクした強度のあるクリエイションを行う自信がありませんでした。ならば「目の前にあることしか出来ない」という現実がそこにあるなら、表現者として、目の前の出来事だけに集中して向き合い、そこから着想を得たダイレクトな表現を行なうべきなのではと腹を括りました。
椹木:闇を抜け、カオスの絶頂として第4章に「変容する日常」があり、そこを抜けると光に満ちたホールで赤子の誕生が祝われるというのは、まさしく生まれ変わるための産道のようです。そこに至るまでの過程があるから、最後の部屋の目が覚めるような明るさがあると思うし、胎内からもう一度現実の世界に帰っていかなくてはという刺激も含めて、たいへん示唆に富む展示だと思いました。

第4章では、群馬県内の廃屋や空き家から残されていた家具を4トントラック1.5台分積み込み、過去のリトゥンアフタワーズやリトゥンバイのアイテムとコラージュしている
山縣:世界が混沌としている中で、現実で起こっていることに直接向き合って作品に社会的なステイトメントを内包して表現する作家が増えましたし、それが世界が必要としている現代における表現だと思うんです。それに対しての、今の僕なりの一つのアンサーとして、これからの表現活動につながるイメージとして最後の部屋は作ったつもりです。僕自身にとっての切実な日常から生まれた単純かつダイレクトな表現「そのままで、行こう」と。
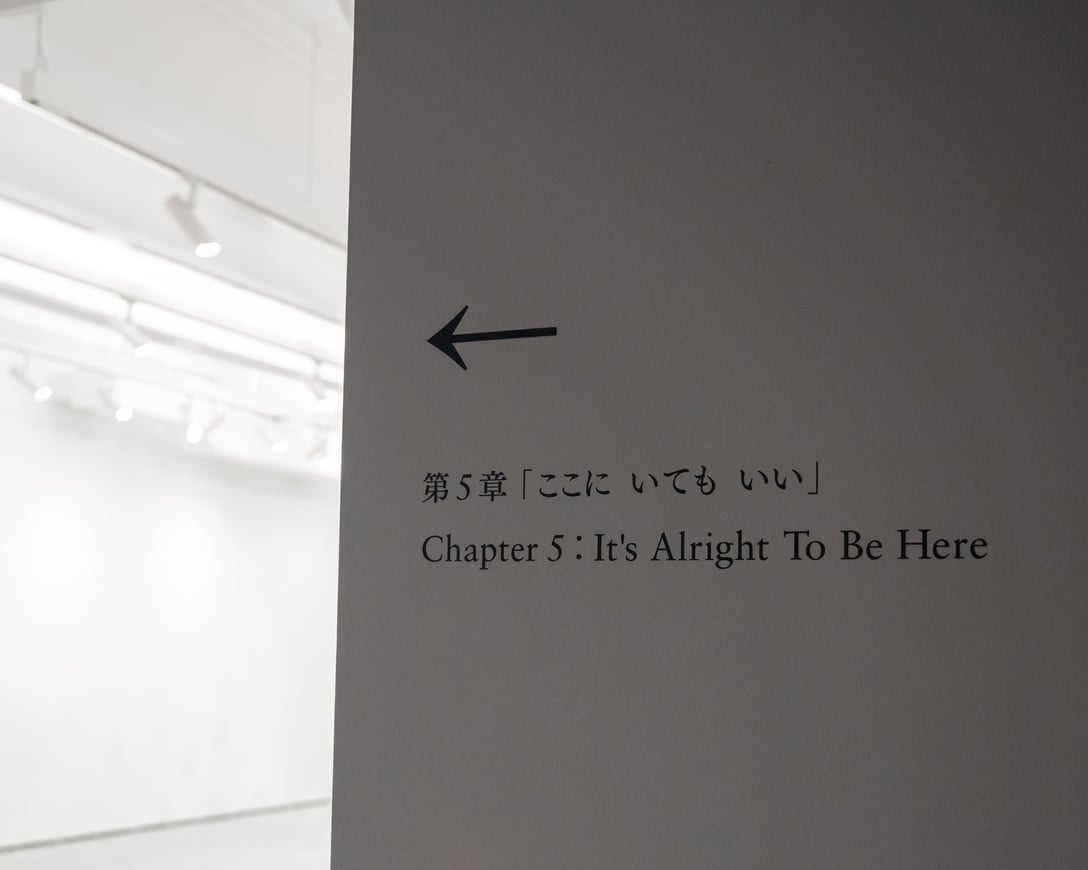
椹木:展覧会のポスターも、息子さんですか?
山縣:そうですね。
椹木:赤ちゃんの後ろ姿で、渦を巻くつむじが写されていますが、改めて見るとこのつむじが渦巻銀河のように見えますね。今、我々が生きている「ここ」というのは、さまざまな天体がひしめく大宇宙の中にあるという、銀河的なスケール感をつい思い浮かべました。
山縣:「ここ」というのは「此処(here)」でもあり、「子子」でもあります。

エレナ・トゥタッチコワが撮影したポスターヴィジュアル
山縣:僕は「ファッション表現」そのものに、ケアの力もあると思っています。何故なら、表現する上で、自分の内なる人間像と対峙し、その像を元に書き替えを行いながら、自分の外側に新たな人間像を創出していくからです。自己の延長線上にある人間像をもう一度客観視しながら、今度はその客観視した人間像をデザインにおいて変幻自在に変えていく。これが「ファッション表現」のもつケアの本質にあります。人は、社会との関係性の中で何らか自己像が傷ついてしまったり、コンプレックスや悩みを抱えています。常に変化する世界と自己を再認識し、さらに可塑的で変幻自在な「デザインされうる存在」と認識すれば、硬直した自己認識と世界を捉え直す事が出来るのではないか、と。そのようなファッション表現のプロセスを通してネガディブケイパビリティが養われ、ケアされることは大いにあるんじゃないか、と考えます。「ファッション表現」の源流に立ち返って、表層の部分だけでファッションを語るのではなく、もっと本質的な可能性や役割にも焦点を当て、これから世界と対峙するものたちが「ここに いても いい」と思える世界になればいいなと願っています。
(聞き手:古堅明日香)
【目次】
本音談義、山縣良和×椹木野衣
1時間目:美術批評家の目にうつるファッション 「制度」を打破しうるもの
2時間目:ファッション(流行)に適した「いま此処」がうつろう日本の土壌
3時間目:ファッションとは儀式で呪術で祝祭である、岡本太郎を例に
ADVERTISING
PAST ARTICLES
【インタビュー・対談】の過去記事
RELATED ARTICLE
関連記事
RANKING TOP 10
アクセスランキング



























