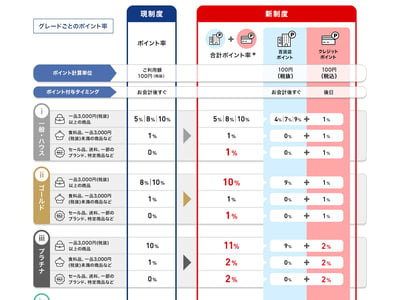今年のお買い物を振り返る「2025年ベストバイ」。16人目は本企画の常連で、13年連続の登場となった繊研新聞社 編集委員の小笠原拓郎さん。毎シーズン、パリをはじめとしたファッションウィークで取材を行う日本を代表するファッションジャーナリストである小笠原さんが今年買って良かったモノとは?
ADVERTISING
目次
SETCHU トラベルジャケット

FASHIONSNAP(以下、F):まず、1点目は桑田悟史さんが手掛ける「セッチュウ(SETCHU)」のトラベルジャケット。でもこんな肉厚の生地のものってセッチュウにありましたっけ?
小笠原拓郎(以下、小笠原):通常はギャバジンの生地で作られている型を、カシミヤ100%で特別に仕立てた1着です。悟史君から「これをカシミヤで作ってみますか」と提案があり実現しました。サイズは3で、パターンは販売されているトラベルジャケットと同じです。通常ラインと違う生産ルートになったので工場の上がりが遅く、6月予定だったのが、最終的に10月中旬に受け取ることができました。
F:上質な生地でとても暖かそうですね。
小笠原:コートいらずですね。特に日本に住んでいると、本当にコートが要らなくなってきていますよね。このジャケットは色々な着方が楽しめるようになっていて、ボタンの留め方でショート丈にもなります。まあ、この丈では着ないですけどね(笑)。裏地は省いてパイピングで仕上げ、カシミヤの風合いを楽しめる作りもいいですよね。


F:セッチュウは、今年1月の第107回ピッティ・イマージネ・ウオモ(Pitti Imagine Uomo)でゲストデザイナーとしてショーを行いましたが、その際のディナー会で小笠原さんは料理メニューを開発されたとか。
小笠原:悟史君にお願いされて、2024年の年末から準備を進めました。フィレンツェの方々に楽しんでもらおうと、和洋折衷をコンセプトに、肉、魚、ベジタリアンの3つのコースを作りました。例えば、フィレンツェのキアニーナ牛のステーキに、柚子胡椒を添えて食べる、といったイタリアの人は多分知らないだろうメニューを作ったり。それのお礼として、特別にこのジャケットを作ってくれたんです。
F:着た感じ、サイズもぴったりですね。
小笠原:実は、袖が長かったので4.5cmほど詰めました。ただ袖口が本開きなため潰すのが嫌で、どうしようかなと悩んでいたんですが、「生地に適度な厚みがあるので肩直しで大丈夫」と信頼できるデザイナーに助言をもらい初めて肩で詰めたんですよ。

F:肩のシルエットもいい感じですね。2024年のベストバイでもセッチュウを選ばれていましたが、セッチュウの魅力とは何でしょうか?
小笠原:彼はプランニングがしっかりしていますよね。ブランドとして次に何をするべきかをちゃんと考えて、ビジネスをクリエイションしている。それは悟史君のすごい才能だと思います。香水を出し、ANAのユニフォームを手掛けるなど、着実に一歩一歩ビジネスを進めている。プロダクトクオリティもすごく高いですし、気候や着方といった今の時代の捉え方がうまい。暑い現代でも快適に過ごせるような提案や、旅での使い勝手、家族で共有できることまで考えて作られているところが魅力でしょうね。今年買ったこのスウェットは彼曰く、LVMHの一押しのポルトガルのジャージー工場で作られており、サイドのジップを外すとゼッケンのようにも着られるんですよ。

F:桑田さんのプレゼン力も含め、ブランディングとクリエイションに弱点が見当たらないセッチュウですが、強いてアドバイスをするとすれば?
小笠原:LVMHとの距離感です。工場や生地の紹介などプラスは大きい一方で、独立した企業としての在り方を維持できる線引きが必要だと本人にも伝えました。自分の意思で売るなら別ですが、意図せずいつの間にか傘下に組み込まれる、ということがないように。
SETCHU クロップド ハカマパンツ

F:続いてもセッチュウですね。こちらは袴プリーツを取り入れたクロップドパンツです。
小笠原:悟史君に「まだ持ってないんですか?」と言われて買いました(笑)。秋冬の物で、くるぶし上のミドル丈。ちゃんとしたジャケットに合いますし、「ヴァンズ(Vans)」のスニーカーでも革靴でもいける。下にレギンスを履いても不自然じゃないですし、歩くとフレアが広がって独特の雰囲気が出ます。
F:ジョーゼットのような風合いがある上質なウール生地ですね。昨年から色は黒が多いですが、色選びのポイントは?
小笠原:黒が増えていますが、気分というより選択肢の問題で、ピンクがあればピンクも着たい。たとえばこの後紹介しますが、「コム デ ギャルソン(COMME des GARÇONS)」のジャケットはピンクに惹かれましたが、欲しい丈のサンプルがなく、価格差もあって黒を選んだという。

F:海外ファッションウィーク中も、小笠原さんはハーフパンツが多いですよね。
小笠原:そうですね。春夏は単純に暑いからですが、近ごろ選ぶトップスとのバランスの関係でクロップド丈やハーフのものが多くなっています。足元はヴァンズ中心ですが、たまに革靴も履きます。ただ最近は革靴が高くなっているから何足かリセールして「イル・ミーチョ(il micio)」でビスポークシューズを作る、なんてことも考えています。
F:桑田さんとは親しい間柄にある小笠原さんですが、ジャーナリストはデザイナーとどのような距離感や緊張関係を保つのが理想だと考えていますか?
小笠原:若い頃はジャーナリストとして緊張関係を強く意識していました。ただ50歳を超え、互いの仕事ぶりを理解し合えるようになってから、親しくても厳しいことを書いたり言ったりできる関係になった。歳の近い「カラー(kolor)」を作った阿部潤一さんとも、やっぱり昔から親しくはあったけど、緊張関係は常にあったなと。「サカイ(sacai)」の阿部千登勢さんもそうだけど。でも、どんどん自分より年下のデザイナーが増えてきて、向こうからするとお父さんぐらいの世代だったりする人もいるわけじゃないですか。父親目線というか、もうちょっとフレンドリーな感じになったところはあると思います。若い頃は怖いとよく言われていましたが、子どもが生まれて、歳を重ねて丸くなったということでしょうね(笑)。今はデザイナーを応援したいという気持ちが強いです。
COMME des GARÇONS アブストラクトジャケット

F:続いては小笠原さんのベストバイでは恒例となっている「コム デ ギャルソン(COMME des GARÇONS)」のアブストラクトジャケット。2025年秋冬コレクションのもので、どうパターンを引いているのかわからない構造的なシルエットが特徴ですね。
小笠原:2015年春夏コレクション「Roses&Blood」、2016年春夏「Blue Witch」の頃のような、いわゆるオブジェ的なものを一度、服の概念の中に戻して表現したシーズンだなと思っていて。以前、川久保(玲)さんが「服ではないもの」「服の概念の外にあるもの」を模索していた時期に、私は「もう一度、服の概念の中で新しさを探すことはできないのか」と問いかける記事を書いたことがありました。そういう意味で、このシーズンは自分の中でのアンサー的な意味を持つシーズンだったので、絶対にこれを買うと決めていました。


F:このアイテムのコレクションではないですが、前回の2026年春夏ショーの翌朝、川久保さんに個別に呼ばれて話をしたと聞きました。
小笠原:ショー翌日の朝一に電話がかかってきて、話したいことがあると言われて。その日は「セリーヌ(CELINE)」がとても遠い会場でショーをする、とてもタイトなスケジュールだったんですよ。でも川久保さんに呼ばれたならと思い、慌ててシャワーを浴びて朝飯も食べず展示会会場に向かいました。話した内容は主にコレクションについてでしたが、普段はバックステージで一言二言喋るだけなので珍しいことでした。川久保さんもコレクションについてしっかり話したかったんでしょうね。

F:少し話を戻しますが、「もう一度、服の概念の中で新しさを探すことはできないのか」と問いかける記事で、小笠原さんが伝えたかったことは?
小笠原:このままでいいのかなって思った時があったんですよ。常に新しいものを追い求めるコム デ ギャルソンが、服の概念の外にあるものを作らないと新しいものができないと考えるのはわかりますが、ショーピースを美術館が買って展示する、顧客はショーピースのエッセンスを着易くした服を買うというビジネスが良いことなのだろうかという疑問がありました。コム デ ギャルソンは、どんなにアヴァンギャルドな服を作っても、それを実際に売るということにプライドを持っている企業だったので。服の概念の外に目を向けたのは8シーズンくらいあったと思いますが、そういう意味で2025年秋冬コレクションは何年ぶりかに服の概念をもう一回追求していくと感じられて。「コム デ ギャルソン オム プリュス(COMME des GARÇONS HOMME PLUS)」の2025年秋冬コレクションもとても良くて、欲しいものはあったんだけど、やっぱりこのジャケットと比べた時に、自分にとってはこちらの方が意味があったんですよね。
F:アイテムの話に戻しますが、こちらはウィメンズサイズですが肩など詰まる感覚はないですか?
小笠原:Lサイズですが、ジャストサイズです。ラペルは普通なんですが、それ以外のパネルが全て斜めに縫い付けられているんですよ。裾もランダム丈になっていますし、おそらく2015年のパターンを再解釈して生み出されたものだと思うんですよね。


COMME des GARÇONS HOMME PLUS チュールショートパンツ

小笠原:これは「コム デ ギャルソン オム プリュス(COMME des GARÇONS HOMME PLUS)」2025年春夏コレクションのパンツで、チュールの部分は取り外しもできます。チュールのジャケットを持っていたので、それと合わせやすいから選んだっていうのもあります。
F:また丈が短いショートパンツですね。
小笠原:でもこれ3クォーターぐらいあって、膝下なんですよ。今は本当に夏が暑いから、男はTシャツに短パンというスタイリングになりがちだけれど、これはインパクト大でシンプルな夏の格好の中に存在感を出せるので気に入っています。

F:これはショーを見て買おうと?
小笠原:そうですね。

COMME des GARÇONS HOMME PLUS」2025年春夏コレクション
Image by: ©Launchmetrics Spotlight

COMME des GARÇONS HOMME PLUS」2025年春夏コレクション
Image by: ©Launchmetrics Spotlight
F:改めて、ファッションショーでは何を見ているんですか?評価する条件など、ショーの見方を教えてください。
小笠原:どういうストーリーなのかを感じられるものがいいショーなのかなと思います。例えば、コム デ ギャルソン オム プリュスの2025年秋冬で言うと、「軍服の解体」というストーリーはすぐに分かります。問題はそれをどういうテクニック、どういうクオリティで、どう見せていくのか。音楽がニーナ・シモン(Nina Simone)で、その歌と演出、最後のルックがはけていった瞬間の静寂まで、完璧なバランスだった。デザイナーがどう考えているのか、そのストーリーがどう伝わるかが大事なんだと思います。
F:デザイナーがどういうものを表現したかったのかを、ショーを見ながらずっと考えているわけですね。
小笠原:そうそう。基本は、上から下までアイテムを見ながらノートに感じたことを書きつつ、最後に「これは何なのか」を言語化する。マチュー・ブレイジー(Matthieu Blazy)による「シャネル(CHANEL)」でも、ダメージ加工の出し方などから、コンサバだけではないマチューの意図を読み解こうと。

F:小笠原さんのノートにはギャルソンのショーにいて「抽象の表現の現在形」と書いてありますね。
小笠原:レイヤードの新表現とかワイドパンツのシルエットも今までありそうでなかったなと、その時感じたことをメモしました。
F:生成AIが発達し、ショーのレビュー記事も書ける時代が来つつあります。人間が書くファッションジャーナリズムで、AIには代替できない要素とは何だと思われますか?
小笠原:難しいですね。30年間ファッションショーを見てきているから、自分なりの見方は確かにあります。そして、それはただ何が出たかだけを書いているわけではない。その時代ごとに持つ意味とか、そういうものをずっと考えて書いているので、そこまでAIが思考できるのかな、とは思ったりします。まあ、でもそういうところはデータベースが補完してくれたらできちゃうのかもしれないけど。今でもプレスリリースなどは結構AIで書けるみたいなことを言う人いるよね?
F:全てをAIで作ることはまだ無理でしょうけど、現状AIを活用していないファッションPRはいないと思いますね。でも結局、ブランドが、デザイナーが誰に書いてもらいたいかということに尽きる気がします。川久保さんが小笠原さんをショー翌日の朝呼んだように、結局ファッションは人と人との繋がりでしかないので。
小笠原:そうですね。いずれにしても、私はあまりAIを使わないので、このままのスタイルでいくと思います。
KIDILL ジャカードニット

F:最後は末安弘明さんによる「キディル(KIDILL)」の2025年秋冬コレクションのニット。ロサンゼルスを拠点とするアーティスト、ブレット・ウエストフォール(Brett Westfall)氏とのコラボレーションアイテムです。キディルも小笠原さんのベストバイ常連です。
小笠原:このシーズンのキディルは非常に良くて。このニットはモヘヤが10%入っているので肌触りもいいですし、ショーでは女性モデルがニットワンピースのように着ていましたが、小学6年生の娘とも共有できるのが購入の決め手となりました。コレクションのアイテム写真を送って相談したら、娘からは「いちごのセーター」一択だと。家族で着られるっていうのは、今結構自分の中で服を買う選択肢としてあるんですよ。ただ、授業参観の時に、娘に着ていく服を指定されるようになってしまいましたが(笑)。ちなみに指定されたのは去年末安君に頂いたキディルのバンビのバックプリントが入ったMA-1です。

Image by: KIDILL

F:英才教育が進んでいますね(笑)。パリで継続的にショーを行っているキディルですが、来場されている顧客も幅が広くユニークですよね。
小笠原:パンクスからスケーター、ギャルまで幅広い顧客を持っているからね。もうキディルは10着くらい持ってます。ロストバゲージでなくならなければ15着くらいになっていましたけど(笑)。
F:海外ファッションウィークはロスバゲとの戦いでもありますね(笑)。キディルもそうですが、今年のベストバイは全て日本人デザイナーのブランドです。
小笠原:これだけ若手のデザイナーがいて、それなりのクオリティを持っている国は日本くらいで特殊だと思っているので、できれば応援したいという気持ちはあります。尾州のウール、和歌山の丸編みニット、浜松の綿織物など、産地もあれば売り先もある。海外だと若手が高品質な工場に簡単にはアクセスできないので、同じようには作れないことも多いですから。セッチュウの悟史君みたいに、20年くらいのキャリアを持って自分のブランドを立ち上げれば、どこでどう作ったらどういうクオリティの物ができるかコントロールできますが、学校出たての若い人にはそれができない。海外だと特にね。
F:それこそ、ミラノなんて全然若手が出てこないですもんね。
小笠原:セッチュウが出るまでは、「エムエスジーエム(MSGM)」や「マリアーノ(MAGLIANO)」くらい?それと比べると、セッチュウやキディルをはじめ、日本からは「ミスターイット(mister it.)」「テルマ(TELMA)」「チカ キサダ(Chika Kisada)」などたくさんいいブランドがありますよね。

F:日本ブランドを買うことが多くなった背景にはもちろんラグジュアリーの価格高騰の問題も?そもそも、今年はあまり洋服を買われなかったそうですが。
小笠原:今のラグジュアリーブランドは、価格設定がクオリティに比べて納得できないものが多すぎる。「これ、原価率10%あるの?」と思ってしまうようなものがいっぱいあって、そんなものにお金は払いたくない。あとは、アーカイヴベースでものを作りすぎているブランドが多く、新しい驚きや価値観を感じるショーが減っているのも買う量が減った原因です。
F:それだったら2024年のようにビスポークのスーツ作った方がいいと。
小笠原:そうなりますね。コム デ ギャルソンが象徴的ですけど、あそこって原価積み上げ方式なんですよ。価格設定の仕方が生地いくら、工賃いくら、物流経費いくら、かけ率いくらとちゃんと積み上げて価格を決めていて、だからプロダクトクオリティに対して納得できる価格なわけです。複雑なパターンで、生地もこれだけ使ったらこの金額になるよなっていう納得があるんだけど、今のラグジュアリーはそうじゃない。為替の影響もあるのはわかるのですが、30年間、服を見てきたからこそ見えてしまうものがあるのですよ。そのため、ラグジュアリーの商品はもう4年は買ってないですね。
今年を振り返って
F:今年のお買い物を振り返ってみて、いかがでしたか?
小笠原:厳選して買ったということに尽きますかね。そこに娘とシェアするという新しい軸ができたという感じです。

娘のために買ったというラブブ
F:今年はジョルジオ・アルマーニさんの訃報ニュースがありました。ミラノファッションウィークの前に、小笠原さんに映画「アメリカン・ジゴロ」を勧められてみましたが、小笠原さんにとってアルマーニさんはどのような存在ですか?
小笠原:テーラリングのゲームチェンジャーですね。肩でホールドしながら、なだらかに揺れるスーツを発明した、それ以前とそれ以降で、テーラリングの概念そのものを変えた人。私が繊研新聞社に入った1992年頃は、世の中のサラリーマンが全員アルマーニっぽい、ちょっと大きいボワンとしたスーツを着ていました。名古屋のサラリーマンも、新橋のサラリーマンも、大阪の金融屋も。繊研新聞の記者たちもみんな同じ格好をしていた。それって本当にすごいことなんですよ。世界中の男たちのスタイルを完全に変えてしまったわけですから。
そして、そのあとのゲームチェンジャーはエディ・スリマン(Hedi Slimane)だと言われた時期もありましたね。近いところでのビジネス的なゲームチェンジャーは、ヴァージル・アブロー(Virgil Abloh)がそうだったのかもしれない。インフルエンサーマーケティング的なビジネスの転換をさせた。それが良い意味のゲームチェンジャーかどうかは分かりませんが。

あと、この間ふと思い出したんだけど、アレキサンダー・マックイーン(Alexander McQueen)が亡くなった時、制作途中だった最後のコレクションを「報道メディアだけに見せる」という機会があったんです。パリのモンテーニュ通りのお屋敷みたいなところの一室に、遺作となるコレクションがずらりと飾られていて。
F:ショー形式ではなく、展示形式で。
小笠原:そう。その時は新聞記者など、本当に限られた「伝えるためのメディア」しか呼ばれていなかったと記憶しています。当時はまだそういう時代だったんですよね。でも今は逆に、マックイーンのショーに新聞社が呼ばれなくなったりもしている。これも時代の流れでしょうね。
F:今年のモード界はデザイナー交代が目立ちましたが、2026年で楽しみにしているものはありますか?
小笠原:引き続き新しいエモーショナルなものが見れれば、とは思いますね。マーケティング寄りではない、エモーショナルなものづくりをしてくれる人が増えることを願っています。あとは、今オーダーしているハットが出来上がるのが楽しみです。帽子ブランド「キジマ タカユキ(KIJIMA TAKAYUKI)」で経験を積んだ黒川望さんの「ノゾミクロカワ(NOZOMI KUROKAWA)」というブランドにお願いしていて。春夏用のハットを作りたくて木島さんに相談していたんですけど、自分がイメージしていた形を黒川さんがドンズバで作っていて。「これだ!」と思って、木島さんに「浮気することを許してください」と断りを入れてオーダーしました(笑)。
F:それは楽しみですね。来年60歳を迎える小笠原さんも、まだまだ新しい出会いに心が動くことがありそうですね。
小笠原:30年も見続けていると、大体のものには出会ってしまっているから、「あの時代のあれの方がいいな」と思ってしまうことも多いんです。だからこそ、本当に心ときめくものに出会えるのは貴重なこと。来年も数は少なくても、意味のある買い物をしたいですね。
◾️小笠原拓郎
1966年愛知県生まれ。1992年にファッション業界紙の繊研新聞社に入社。1995年から欧州メンズコレクション、2002年から欧州、NYウィメンズコレクションの取材を担当し、30年以上にわたり世界中のファッションを取材執筆している。
繊研新聞
最終更新日:
ADVERTISING
PAST ARTICLES
【買ったモノ】の過去記事
RELATED ARTICLE